
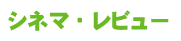
| ストーリー | キャスト | 感動感銘度 | 大人度 | 印象度 | 総合 |
| 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 76 |
※各項目は5点満点、総合は100点満点
ええと、新年から病気になる話です。
昨年の映画だったけれど、岡山ではまさに今公開中なので、タイミング的に新年からの鑑賞になってしまいました。
大林宣彦監督作といっても、しょせん病気ものでしょ?なんて思っている人もいることでしょう。世の中には、病気もので泣きたいと思っている人もいるだろうけど、人が死ぬような話で感動(?)したくないよなあと思う人も大勢いるものです。
余命いくばくもない妻、それを見守る夫と家族が静かに描かれて・・・という題材では、なんとなく観なくても内容は分かるような気がします。
でも。冒頭で浮かび上がる懐かしい「A MOVIE」の文字を観てから、一気に大林宣彦の世界に引き込まれます。こういう題材であればこその監督の手腕なんですね。
上空に描かれる飛行機雲、それを見ている南原清隆演じる夫の表情、とまあ普通に始まったと思ったら、荒波たけり狂う海でのスペクタクル巨編のような映像やら、顔を引きつらせながら階段を駆け下りてゆく南原清隆のサスペンス映画のような雰囲気など、時にはなんだか笑ってしまうような映像表現満載ながらも、深刻な病を告げられる妻とその夫との日常、さらには謎のクラムボン君の歌うとても印象的な宮沢賢治の詞に曲をつけた『あめゆじょとてちてけんじゃ』などなど、大林映画要素満載です。
だいたい、観てから一週間たったのに、『あめゆじゅ〜』なんて未だに耳から離れません。「時をかける少女」の『ももくり、さんねーん』や、大胆にもショパンの別れの曲に詞をつけた「さびしんぼう」の『さーよならぁ』などの例から考えると、これは一生耳に残ってしまいそうです。
どこが原作要素で、それをどのように映画表現としているのか原作を読んでないから分からないけれど、こういう表現の積み重ねは映画ならではだと思うので、それだけ映画になっていることの意味を感じます。
この深く心に堆積していく感じが、やはり映画を観たときの感慨です。
死を描きながらも、永作博美演じる妻の屈託のなさが、じめじめした感じを払拭しているのと同時に、逆に"その日"を強く意識させます。
結婚してからしばらく住んでいた町を久しぶりに二人で訪れるというエピソードは、この町で暮らした若い頃の二人、さらには海での同級生行方不明事件との接点になっていて、これがお盆の花火大会につながっていきます。
生者と死者、現在と過去が、渾然一体となっているこの映画は、永遠の別れである死の残酷さを表現するだけではなくて、生きている者が思い出すことによっていつでも生きているときと同じような時を過ごすことができるという希望を与えてくれます。
思い返すと、男と女、現在と未来と過去、親と子、死者と生者などを描きながら、常に大林監督は、固定した関係ではなくて、それをひっくり返して、逆の視線から観ることを撮り続けていたような気がします。
話の本筋の妻と夫よりも、観終わって思い返すと、なんだかその周辺の人物や出来事の方が強く印象に残っている映画です。
シネマ・クレール丸の内1にて
−2008角川映画/139分−
シアターF.通信