
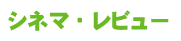
予告編から涙が溢れそうになってしまったのって、「チョコレート」以来かも。
映画でも、冒頭のマザーテレサが若い母親と子供に歩み寄って祈りを捧げる場面で、その慈愛に満ちた表情に胸が締め付けられます。
今は、慈愛よりも自愛の人が多いものね。
こういう"清く正しい"映画は、どうもなあと思っていても、このような魂の奥底に触れてくる作品に触れるのもいいと思います。
理想に生きるということが、野暮ったいと思われがちな今こそ、このマザーテレサの生き方に、純粋に感動します。
インドという困難な土地にあって、修道院という守られた建物に囲まれた中ではなく、街に出て、しかも最下層の人々のために働いた彼女の純粋なまでの行動。
前半は、マザーテレサの行動が、従来の修道院という枠組みに納まりきらなくなり、新たな修道院を作るために奔走する彼女が描かれます。
(観てから読んでね→)
こうしてみると、カトリックの世界も、自由が利かないというか杓子定規というか官僚的ですね。でも、彼女の怒りの矛先は、そのような組織へは向かないんですね。かならず、マザーテレサの熱意に動かされて、いい方向に行っているし。
かなり断片的なエピソードの積み重ねだけれど、マザーテレサの人となりは十分に分かります。
本当に常に他人のために奉仕した人なんですね。
最後の、「慰められるよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されるよりも愛することを。与えることにより与えられる」という言葉が沁みてきます。
大体、癒されたいなんて、卑しい考えですよね。
(←ここまで)
マザーテレサを体現したかのようなオリビア・ハッセーは素晴らしいと思います。インドの喧騒とともにある彼女の意思が輝いてます。
シネマ・クレール丸の内にて
−2003伊・英/116分−
シアターF.通信