
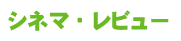
この映画の主題はとても重い。若い頃に事故により首より下の体が麻痺してしまった一人の男・ラモン。惨めな生よりも、尊厳のある死を選びたいと思っているが、体が麻痺しているため、死を選ぶためには誰かの協力がいるのだ。
いきなり死を望まれたって、介護していた家族は戸惑ってしまう。
老いた父親の、"息子が事故で四肢麻痺になってしまっただけでも悲しいのに、さらに死を望むとは・・・"という意味の言葉が身に沁みます。
彼の父親、兄、兄嫁、甥といった家族、彼の尊厳死を勝ち取るための訴訟を担当する弁護士、そして、彼の尊厳ある死を望む姿勢に惹かれてやってくる女性。
彼を取り巻く人々は、さまざまな反応をします。倫理的には、死を望むという姿勢が許容できなくても、二十数年間にもおよぶ、彼のベットに横たわったままの人生を前にして、死を望むというか、権利として死を選ぶ姿勢の強さに、たじろいでしまいます。
この死を主題としていながら、このラモンの前向きな姿勢はどうでしょう。死に向かって前向きと言うか、すべての積極的な行動が死に結びついていくという、なんともいえない違和感があります。
死を望む自分を批判するなとラモンは言うが、自分ならどうしただろう。それでも、生きろと言ってしまったかもしれない。
(観てから読んで→)
結局、ラモンは望みどおりの死を迎えることができたのだけど、死を迎える最後の最後に、後悔はなかったのだろうか。安らかに死を迎え入れることができたのだろうか。
"海を飛ぶ"ということは、ラモンにとって、若いときの事故の悔恨があったのでしょうね。海を飛ぶことが出来さえしたら、あの事故をもなかったわけだし。何で引き込まれるようにして飛び込んでしまったのか。
病に侵された弁護士の最後の姿は、尊厳のない生かもしれないけど、彼女の生に対しても批判はできない。
誰しもラモンみたいな強い心ではないもの。
(←ここまで)
シネマ・クレール丸の内にて
−2004スペイン・フランス/125分(PG−12)−
シアターF.通信