
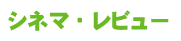
13歳の夏に僕は生まれた << 2006レビュー >> 夜のピクニック
冒頭のフィルムパートナーズとやらに、やたらと名前を連ねている企業群。こんなにずらずらと・・・すごいものです。
太平洋戦争末期、爆薬を搭載し、人間が操縦してそのまま敵艦にアタックするという秘密潜水兵器"回天"での任務を与えられた学徒出陣の若者たちの運命の物語です。飛行機での特攻隊があったように、海軍でも同じような特攻があったんです。
訴えたいことはわかるんです。この映画の中でも言っているように戦争中"回天"という兵器がありそれで命を落とした若者たちがいると・・・。それを伝えたいと・・・。
でも、映画という手段でそれを訴えるのであれば、受け止める側もやはり映画として評価しなければなりますまい。
六大学野球で活躍した投手という経歴を持つ主人公には市川海老蔵という異色(でもない?)の配役。
その恋人に上野樹里、それから同じ大学のニヒルな敵役に伊勢谷友介といった若手の注目株を配し、潜水艦艦長に香川照之、海老蔵の父親に三浦友和といったベテランを起用したキャスティング。でも、ちょっと言いたいこともあるんです。
(観てから読んでね→)
まずは、市川海老蔵。やたらとぎらぎらした印象が強いだけに、この役のように特攻を志願するというちょっと油の抜けたような役がちょうどいいような感じですが、普通にしゃべるセリフのいちいちになんだか不自然さを感じます。
上野樹里にしても、ここに彼女を使う必要はないんじゃないかなあ。「チルソクの夏」の頃ならまだしも、最近の彼女はひょうひょうとした軽妙な味わいを生かす方向性を出しているだけに、ここで死にゆく海老蔵が思いを寄せる人という役柄でもってこなくてもと思います。もっと他に女優はいるでしょう。
映像としても、潜水艦内部のシーンは良いものの、引いた画となると、とたんにそのスケール感の乏しさを通り越したチープさが露呈して、たそがれの日本映画的な画面に悲しくなります。
学徒出陣の場面も昔の映像の挿入であるし。
予算がないならないなりに、観ていてがっかりというか寂しくなるということがないような画作りをしてほしいんですけど。
根本的にこの映画の監督としても、佐々部清の起用というのは適切な判断だったんでしょうか。
陸地での日常シーンは佐々部清に適していると感じるけれど、戦闘シーンは少ないながらも潜水艦内部を含めた戦闘場面は、佐々部清の資質とあっているかは疑問です。
「半落ち」と同じ横山秀夫作品だから佐々部清、だとか、山口県が舞台だからここは佐々部清、というようなノリではないんですよね。
最後に、かなり佐々部清調が出てしまうんですが、これは映画に与える効果としてはどうなんでしょうか。
なんか言わずもがなという印象を持ってしまいます。いや、これがあるから現代からあの戦争の時代に対しての視線が生じるのだという人もいるとは思うけれど。
(←ここまで)
なんか、最近、文句ばっかり言ってますね。
しかし"回天"という兵器は、とてつもなく操縦が難しかったようです。故障も多いし。
整備も大変、操縦も大変というこの難物兵器を、厳しい訓練の末ようやく制御できるようになっても、その熟練操縦士は、兵器と共に死んでしまうというんですから。
死ぬために、技術を向上させていくというのはどういう気持ちだったのだろう。
"お国"のため・・・そんな言葉で国民の命を簡単に奪っていくわけです。
提唱されている"美しい国"も、美しい"お国"っていうとかなりおもむきが変わります。
TOHOシネマズ岡南スクリーン9にて
−2006松竹/121分−
シアターF.通信
13歳の夏に僕は生まれた << 2006レビュー >> 夜のピクニック