
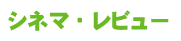
出口のない海 << 2006レビュー >> もしも昨日が選べたら
恩田陸の名作と言われている「夜のピクニック」の映画化作品です。
本屋大賞の映画化としては、「博士の愛した数式」に次いでの映画化なわけです。公式HPには"全国の書店からのコメント"というのがあって、本屋大賞っぽさを出していますね。
原作はいいタイミングで、文庫化されたりしているけれど、一般の盛り上がり度はどうなんでしょうか。
一昼夜をかけて、80kmを歩くという「歩行祭」というイベントを通して、高校時代のリリカルな心情を綴るという、設定からして心惹かれる原作だったわけですけど、さて映画はどうなの?というところです。
高校生のお話なので、キャストも若手が中心です。
歩行祭に一大決心をもって望む貴子には多部未華子、そして融には「蝉しぐれ」の石田卓也。そのほかに、郭智博、西原亜季、貫地谷しほり、松田まどか、加藤ローサ、柄本佑、高部あい、近野成美。知ってる人も知らない人もいるけれど、この若手の中で誰が有望株なのかということを探るのもこの映画の一興です。
個人的な株価観測は、多部未華子→、石田卓也↓、貫地谷しほり↓、加藤ローサ↑、柄本佑↓といったところで、うーんなんだか下げが目立つんですが、彼らのせいなのか、この映画の出来のせいなのかはよくわかりません。
というか、この監督(長澤雅彦)の製作姿勢に大いに疑問を感じてるんです。
(観てから読んでね→ <読む場合はカーソルでドラックして反転させてください>)
インタビューによると、この監督は、歩行祭のエキストラへの指示に追われて、まともに役者に演技をつけなかったそうですね。
しかも「役に合っているから(その人を)選んでいるので、何も別の者になってほしいと思っているわけじゃないので」っていって、信頼関係だかなんだか知らないけれど、はっきりといってしまえば、手抜きを開き直っているかのような言動もあったりして、この仕事ぶりには不信感が増大です。
まあ、5000人近いエキストラ1人1人に、キャラクターの設定をし、その設定を書いた紙を渡して演出していたそうですが、そんなことしたら、肝心の役者にまで手が回らないのも当然ですかね。
このこだわりが凄いと思うか、そんなことしている場合かと思うか、いろいろと受け止め方もあるわけですが、でも、これって本末転倒でしょう。そういうこだわりが映画の中でリアリズムを構築するのになんらかの役に立ったんでしょうか。
いちゃいちゃカップルだとか、馬のかぶりものだとか、背景人物として、色々出てくるわけです。「HINOKIO」でのパソコンゲームにはまってしまう眉毛の男の子なんかも観られます。
そうであれば、杏奈の弟は本郷奏多でもよかったという声もありそうです。柄本佑がツライ・・・。まあ、原作でもこういう感じだったので体現しているんでしょうけども。
ロケ地に関することについても、「やっぱり、物語が生まれた場所には何かがあるだろうなと。(略)ロケの候補地もいろいろあったんですけど、空想だけで作ったものではないので、やっぱりその場所でやろうと思いました」って、なんかすべからく手抜き発言に思えてしまいます。
どうりで、歩いている最中の、海だとか田園風景だとか夜空だとか、そういう風景の素晴らしさも感じ取ることはできないわけです。撮り方もおざなり?
要は、エキストラ揃えて歩かせて撮影するだけで精一杯で、他の事には一切手が回らなかったということなんですか。
こんな監督に付き合わされた若手俳優もかわいそうだし、観客である我々もかわいそうです。
監督にほっておかれた多部未華子の不安な心情も分かります。若手が多いんだから、もっと丁寧な演出が必要なんではないでしょうか。偉そうですけど。
「並んで一緒に歩く、ただそれだけなのにどうしてこんなに特別なんだろう」というセリフがあるけれど、これにならって言えば「並んで一緒に歩く、ただそれだけのことなので、映画にするとなんて退屈なんだろう」というようになってませんか。
(←ここまで)
個人的には、原作もそうだけど、登場人物がなんでこんなにノスタルジー気分なんでしょう。思い出づくりのようにイベントを消費するという、それが今時の気分?なの。
TOHOシネマズ岡南スクリーン4にて
−2006ムービーアイ=松竹/117分−
シアターF.通信
出口のない海 << 2006レビュー >> もしも昨日が選べたら