
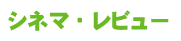
敬愛なるベートーヴェン << 2006レビュー >> パプリカ
この映画のすごさは、本編が終わってエンドロールになっても、誰一人として席を立たず、ざわめきもなかったことでよく分かります。明かりがついても、数秒間は静まり返っていたもの。こんなこと映画を観てきて、初めてです。
硫黄島の戦いを描いたこの映画は、日本人として自尊心をくすぐるということではなく、また戦争の悲惨さというひと括りの言葉ではなく、また日本とアメリカとどちらがよりひどい事をしたかということではなく、まさに戦争という状況での人間のドラマを描いています。
アメリカ映画でありながら、キャストは渡辺謙、二宮和也、中村獅童、伊原剛志、加瀬亮といった日本人俳優であり、全編日本語セリフ、さらにはクリント・イーストウッド監督であるというのは、観ている最中は気にならないけれど、よく考えるとすごいことです。
それぞれの役に対して、バックグラウンドも丁寧に描くことによって、彼らの置かれた立場が鮮明になります。
戦場というのは、職業として軍人を選んだ者と、徴兵されてやってきた者とが混在する場所であって、それぞれの感じ方は大きく異なることが分かります。でも、それは表面的な違いであって、それを表に出すのか出さないのかの違いだけのような気もします。
パン屋を営んでいた西郷は、徴兵されて硫黄島にやって来た方の代表です。かなり合理的な判断をする人間なので、軍の非合理さとは相容れない部分があるんです。
理不尽な懲罰を受けている西郷を幾たびか救うのは、新任の司令官としてやってきた栗林中将。栗林は戦前にアメリカに行ったことがあり、アメリカの国力がよく分かっているんです。
硫黄島にも、アメリカが圧倒的な戦力でやってくることも分かっている。希望的な観測もしない彼は、むやみな絶望もしない。その時に栗林のとった戦術は、玉砕戦法ではなくて、徹底的な持久戦です。
敵の実力、自分の戦力という現実を冷静に見極めて、それに対して効果的な手段を考える。
この彼の戦法が、一方的な殺戮になったかもしれないこの戦いを、戦闘という形に持ち込むことができたわけです。
一兵卒と司令官、西郷と栗林とでは立場が違うけれど、合理的な判断を重視するというところでは一緒です。
でも、この戦いはあまりにもひどい。補給はなく、空と海からの援護もない。
こんな状態で戦わなければならない彼らの運命の厳しさに慄然とします。これが戦場というものなんですね。
感じるのは、深い憤りです。
憲兵であった加瀬亮のエピソードなど、多くの印象的なシーンがあります。
西郷を演じた二宮和也の演技が、予想以上に良いですね。
裕木奈江は、久しぶりです。かつてはぶりっ子的なありようが批判されたりもしていたけれど、海外で頑張っているんですね。
TOHOシネマズ岡南スクリーン6にて
−2006米/ 分−
シアターF.通信
敬愛なるベートーヴェン << 2006レビュー >> パプリカ