
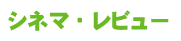
この時代設定はいつなんでしょうか。
柴咲コウ演じるハイパーレスキュー隊員が子供の頃に阪神大震災で被災した人間だという言及があるので、これは現在(2006年)以降の話だと思いますが、映像にはオリジナル版の公開された昭和48年的な雰囲気が満ち溢れています。
タイトルバックが昭和40年代的なのはオリジナルへのオマージュということでいいですが、本編の中でも錯誤するかのような昭和的な映像はどうかと思います。なんか混乱します。
一瞬、オリジナルの時代設定にしているのかと思ってしまった。
さらには、この日本の佇まいに対しての愛惜さえ感じる描写は一体どうしたことかと思ってしまいます。同じ樋口真嗣の手になる「亡国のイージス」では、こんな日本は滅んでしまえといわんばかりの描写にあふれてましたが・・・。
これが小松左京と福井晴敏の違いでしょうか。それとも製作に携わる毎日新聞と産経新聞の違いでしょうか。
何はともあれ、冒頭の静岡の大地震から、日本の異変は始まるんです。
映画のドラマは大きく三つの流れで進んでいきます。
まず一つ目は、柴咲コウと草なぎとのシーンを中心として、下町の人々の生活者シーン。
そして二つ目は、日本の危機的状況をいち早く察知する田所博士演じる豊川悦司(このキャラクターは好きです)、潜水艇のパイロットのくさなぎ、及川光博の調査、探索シーン。
そして三つ目は、総理の石坂浩二、危機管理大臣の大地真央、官房長官の國村隼の政府シーン。
この三つのドラマの合間に各地での災害があるんですが、これは日本各地災害案内のような感じで、なんかドラマ部分とかみ合ってないように感じます。
日本の形がどんどんと変わっていくという部分に、子供の時分は恐ろしさを感じたものですが、こんなに変わっているのに、なんかドラマ部分の人々はそれとは関係なく動いているような気がしてしょうがありません。
というのも被災する人々のドラマがないからでしょう。
特にかつてのTVドラマ版では、雪祭りとともに大通公園で沈んでいく老人だとか、オホーツクの海で流氷の割れ目から転落してしまう女の子だとか、災害に遭遇するまでのドラマが強烈な印象を残しただけに、この映画では災害の描き方は、人々が集まっているところに、大津波がわーっ、地震がゴーォでしょ。
なんかちょっとでも被害にあったそれぞれの地域での人々のエピソードを盛り込めなかったんでしょうか。
(観てから読んでね→)
田所の予測通り沈んでいく日本。最後の切り札としてプレートの切断を狙って、その起爆のために潜水艇が使われるわけですが、及川光博は別として、草なぎ剛は生き残って欲しかった。ご都合主義と言われても、なにか理屈をつけて戻ってきて、柴咲コウと結ばれるという展開がよかったなあ。
及川と共に沈んだしんかいに予備電源が残っていたとか、なんとでも理屈は付くでしょう。なんか、日本を救うために犠牲になったというところが後味が悪い。
といいつつ、柴咲コウと草なぎとのシーンは、テントの外で、そしてテントの中で、そしてヘリコプターで出発するところでと、同じような情感のシーンの連続で、なんかまどろっこしい。それでいて、お互いの気持ちを確かめてから、それぞれの別離のシーンまでが短いので、感情移入も出来づらい。そもそも恋心を抱くようなきっかけはなんだったんでしょうか。
というわけで、なおさら草なぎにここでいなくなられると不完全燃焼的な気持ちになります。悲恋というところまで盛り上がるわけでもないし。
最後の、首相代行のような声明文の読み上げは、なんかアメリカ映画を彷彿とさせます。
結局、日本はすんでのところで助かったわけで、東スポ的に、日本沈没!・・・・・(折り返し部分にちいさく)か?という感じでしょうか。
(←ここまで)
かつての日本沈没は地震列島に住まうことに対しての恐怖をダイレクトに呼び覚ましたけれど(関東大震災から50年だから、東京に大地震が起こるといわれたりしてたものね)、本作の日本沈没は、災害による沈没ということだけでなく、経済的や国際的な地位に対しての沈没というイメージを色濃く喚起します。
ちょっとイヤな部分です。
TOHOシネマズ岡南スクリーン6にて
-2006東宝/135分-
シアターF.通信