
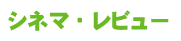
アサルト13 要塞警察 << 2006レビュー >> 空中庭園
「戦場のピアニスト」のロマン・ポランスキーが、次の題材に選んだのは、チャールズ・ディケンズの小説なんですが、まずは、この「オリバー・ツイスト」という作品を"今"映画化する意味を問いたいんです。
確かに19世紀のイギリスを舞台にした街のセットなんかは素晴らしいと思うのです。かつては本当に馬が交通手段の主役であったんだなあとか、表通りだけでなく、裏通りの整備されていない状況など、この今の日本に居ながらにして見ることができるのは、映画ならではです。
そして、この物語の主役の男の子であるオリバー・ツイストの不幸な境遇に、深い同情を寄せてしまいます。
観た直後は、この作品を作った意味(というか作品そのものの意味もだけれど分からなかったんです。
そういえば、「プライドと偏見」は18世紀イギリスが舞台で、この19世紀イギリスものと並んで、イギリスでは時代物ブームなんだろうかという感想しか浮かんでこない始末・・・。
でも、こういう見方も出来るのかもと思い至ったのです。
オリバー・ツイストは、運命を積極的に切り開いていくという話ではない。だけど、弱者が、自ら運命を切り開いたり、戦ったりしていけるわけではないでしょうということなのかも。あまりにも我々は、果敢に戦ったり、道を切り開いたりするヒーローに影響されすぎているのかもしれません。
親のいない状況に育ち、そして救貧院にいても将来の見通しは立たず、大人たちはそんな子供の将来のことなんて考えてもくれず、そんな状況中で、オリバー・ツイストは育ったわけです。そうであれば、とりあえず、そのどうにもならない状態から、逃げるという手段しかないのだろうと。
そして、その後は、人々の善意と悪意の狭間である意味流されながら生きていくほかに何ができるのかと。
そんなふうにこの映画は言ってるよう気がします。
そうすると、「戦場のピアニスト」でも主人公は逃げ回っているばかりで若干の物足りなさを感じたけれど、彼にしても戦場という極限状態で、いったい逃げるほかに何ができたのかということに思い至れます。
普通の人々にとって、とりあえず逃げるという手段を選択することは、最悪な状況に対抗するには最善の手かもしれません。逃げるということをネガティブなイメージで捉えるのではなくて、弱者の選択としてもっと評価してもいいんです。
とにかく、逃げろ!ということなんですね、この映画化の意味は。
無意味な勇気を鼓舞するよりは、この生き残るために逃げろという映画は、とても良心的です。なんで逃げなかったんだろうというような事件が多すぎる現代にはなおさら、そう思います。
岡山メルパ2にて
−2005仏・英・チェコ/129分−
シアターF.通信
アサルト13 要塞警察 << 2006レビュー >> 空中庭園