
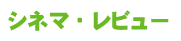
なんだか、中国映画ではなくて、まるで日本映画のような感じじゃないですか。
これって、チャン・イーモウの映画に高倉健が出たのじゃなくて、高倉健主演の映画をチャン・イーモウが監督したという位置づけですね。理解が間違ってました。日本の風景なんてまるっきり捉え方が日本映画だし(と思ったら、日本パートは、日本人スタッフが撮影してるんですね。日本編監督は降旗康男です)。日中合作という感じですね。
そういうことも含めて、なんか、チャン・イーモウのスタイルが見えてきません。さすがに、中国の内陸に向かってからの田舎の風景、人々、そしてあの男の子ヤンヤンはチャン・イーモウの独壇場という感じだけれど。
高倉健とチャン・イーモウが会したという、その組み合わせを賞賛する映画です。
でも、文化的な差異があって、それをさらに乗り越えるというような展開が欲しかったと思います。今日のようになってしまった日中の関係であれば、なおさらじゃないでしょうか。
善意と善意とで、まごころとまごころとだけでこれだけの繋がりをもてるとは、ファンタジーではあるけれど。
国と国とが心を通わせることより、親と子が心を通わせる方が難しいのかもしれないと思わされます。
高倉健演じる父親と、声だけの出演ではあるけれどその息子を演じる中井貴一と。これだけ関係がこじれてしまったからには相当の事があったのかもしれないけれど、意外と小さな行き違いの積み重ねがそうさせてしまったのかもしれない。
それとも、この父と子というモチーフは、中国と日本というものを投影しているんでしょうか。それは考えが飛躍しすぎ? でも、そう考えるとかなり腑に落ちる部分も多々あります。
まあ、それはそれとして、子供との絶縁、そしてその絶縁に対する後悔の念には、親の立場にある人は自分の姿を多かれ少なかれ重ね合わせるのかもしれません。
この中国の田舎の風景は、中国の現代にとってもノスタルジーになりつつあるのかも。お金を返すガイドであったり、一人の異国からの旅人に対して村全体で歓待するということも含めて。
中国の人々は高倉健が心情を吐露すると惜しみなく便宜を図ってくれたりして、旅に際しての障害は意外とありません。対立がないんです。
こんな時代だからこそ、真心が通じるというファンタジーをチャン・イーモウはとりたかったんだと思います。
ジョリー岡山東宝にて
−2005東宝/108分−
シアターF.通信