
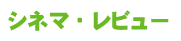
サムサッカー << 2006レビュー >> ただ、君を愛してる
この間、NHKスペシャルでもやってましたが、太平洋戦争末期の硫黄島を巡る日米の戦いは地獄のようなありさまであったんですね。
アメリカは短期間で攻め落とせると思っていたのに、島に掘り巡らしたトンネルを使った玉砕覚悟の日本軍の戦術に手を焼き、アメリカ軍も多大な損害を受けた硫黄島の戦い。
この番組では、食料はおろか水もなく地獄のようなありさまの硫黄島の戦いを生き残った元日本軍兵士の「戦友の死は無駄死にだったんだろうか、でもそうは思いたくない・・・」という問いかけが重かったんです。
この映画「父親たちの星条旗」は、次に公開される「硫黄島からの手紙」と合わせて、硫黄島での日米の戦いを描く二部作となります。監督のクリント・イーストウッドは、この二作でアメリカ側と日本側双方の視点から、この戦争を描こうと試みます。
でもですね、硫黄島を舞台とした迫力の戦闘シーンというようなものを期待していくと、ちょっと肩透かしをくらうかもしれません。
この硫黄島での戦いを過去を振り返るという視点から始まり(だから「父親たちの星条旗」なんですから)、<硫黄島での戦闘を行っている時点>、<硫黄島から帰ってきて英雄として迎えられた時点>、<遥か後年の年老いた時点>の三つの時間を行き来します。
もちろん、場所的にも、硫黄島、そしてアメリカ本土ということになり、ボリューム的にアメリカ本土のシーンの方が多いくらいかもしれません。
主人公は、硫黄島で戦い、有名な星条旗を押し立てる写真に写った兵士たち。
(観てから読んで→)
彼らは本国へ帰ってきてからは英雄として扱われ、アメリカ中を巡回して、戦費調達キャンペーンの一役を担わされるわけです。
でも、このイベント的な扱いと、あの硫黄島での壮絶な戦いとのギャップに苦しむ彼ら。表面的に国家の英雄として扱われるけれど、英雄なんかじゃないという気持ちだったのでしょう。
(←ここまで)
冒頭で、次々と、名前と階級のテロップとともに現れる兵士たち。
登場する人物の顔と名前とを、瞬時に頭に叩き込むのは苦手です。俳優の顔の区別がつかず、名前と顔が一致しないという状態になってしまってました。戦場ものに対する弱点です。
でも、言い訳をするわけじゃないけど、外人の顔っていうのは区別がしづらいですよね。おまけにヘルメットかぶっているわけで、余計特徴を掴みづらい。
なんだか、誰が誰だか分からずに、回想でも誰のことを言っているのかが分からずじまいのところがあり、理解の大きな妨げになっていたわけで、大いなる反省です。
TOHOシネマズ岡南スクリーン2にて
−2006米/132分−
シアターF.通信